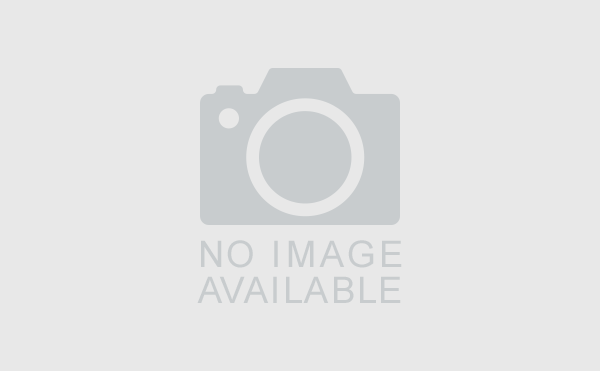◆今月の経営格言 福澤諭吉(慶應義塾創設者)
[セミナー名] 退職金制度の見直し方セミナー
[資料等] 44ページ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 9月5日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
10月3日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 26,000円(税別) 28,600円(税込)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/004_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****[退職金制度の見直し方セミナー申し込み書]***********
日 程 下記にご希望日時をご記入ください。
月 日
社 名
役職名
氏 名
参加数 人 (人数は不問です)
電 話
*************************************************************
日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
調整できます。上記にご記入ください。
☆★☆―――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年8月13日 VOL.5320
――――――――――――――――――――――――――――
今年は関東大震災が発生してから、丁度100年となる年です。
続きは編集後記で
――――――――――――――――――――――――――――
◆今月の経営格言 福澤諭吉(慶應義塾創設者)
――――――――――――――――――――――――――――
◆今月の経営格言
「見込みあればこれを試みざるべからず。いまだ試みずして
まずその成否を疑う者はこれを勇者と言うべからず」
福澤諭吉(慶應義塾創設者)
出所:「学問のすすめ」(中央公論社)
――――――――――――――――――――――――――――
冒頭の言葉は、
「たとえ実現が困難と思われるようなことであっても、少し
でも成功する見込みがあれば、積極的に取り組まなくては
ならない」
ということを表しています。
福澤氏は、幼い頃から漢学の分野で非凡な才能を発揮していま
した。しかし、中津藩の下士という低い身分の家に生まれた
ため、門閥制度が厳しい藩内では能力を発揮する場が与えられ
ませんでした。このため、藩を出ることを決意し、長崎での
留学を経て大坂の蘭学者緒方洪庵の適塾に入り、蘭学の習得に
努めました。
1858年、福澤氏は中津藩の命を受けて江戸で蘭学塾を創設しま
した。その後、開港して間もない横浜を訪れ、世界ではもはや
オランダ語ではなく英語が主流となっていることを知り、独学
で英語の習得に取り組みました。
こうした中、1860年に江戸幕府が米国に使節団を派遣した際、
福澤氏も随行して渡米し、西洋文明に触れて大きな衝撃を
受けました。その後、1862年には欧州への使節団として諸国を
視察し、議会制度や医療制度、教育制度などさまざまな海外
事情についての見聞を広め、帰国後に自らの渡米・渡欧体験を
基に『西洋事情』を出版しました。
『西洋事情』は、西洋諸国の社会制度や文化、技術、歴史など
について体系的に解説した書籍です。厳しい封建制度の下、
加えて依然として攘夷の機運が残っていた当時、西洋文明に
ついての理解を得ることは困難であり、命さえ狙われかねない
危険をともないました。
しかし、福澤氏は、近代国家としての日本の創造において西洋
文明の導入が不可欠であることを確信し、西洋文明を広く人々
に知らしめるべく啓蒙活動に情熱を傾けたのです。
こうして、その後全10冊にわたって出版された『西洋事情』は、
当時しては空前のベストセラーとなり、幕末の日本人および
新生日本の誕生に多大な影響を与えることとなりました。
福澤氏は、学問においてしばしば「実学」という言葉を使い、
次のように述べています。
「学問の要は活用にあるのみ。活用なき学問は無学に等し」
学ぶだけでは学問を修めたとはいえません。学んだことを実際
の行動に生かすことで学んだことが生きてくるのです。この
福澤氏の実学の精神は連綿と受け継がれ、現在の慶應義塾大学
の教育理念として根付いています。
積極的な挑戦を続ける姿勢と、そこから得られたものを実践
する行動力。この二つの精神によって、学んだことを最大に
生かすことができるのです。
【本文脚注】
本稿は、注記の各種参考文献などを参考に作成しています。本
稿で記載している内容は作成および更新時点で明らかになって
いる情報を基にしており、将来にわたって内容の不変性や妥当
性を担保するものではありません。また、本文中では内容に即
した肩書を使用しています。加えて、経歴についても、代表的
と思われるもののみを記載し、全てを網羅したものではありま
せん。
【経歴】
ふくざわゆきち(1835~1901)。
大坂(現大阪府)生まれ。
1858年、江戸(現東京都)で蘭学塾(現慶應義塾大学)設立。
1872年より「学問のすゝめ」刊行。
【参考文献】
「学問のすすめ」
(福沢諭吉、中央公論社、1984年7月)
「福翁自伝」
(福沢諭吉(著)、富田正文(校訂)、岩波書店、1978年10月)
「福澤諭吉旧居・福澤記念館」
(公益財団法人福澤旧邸保存会)
(中川コメント)
本日の記事は弊社が有料会員となっている「中小企業福祉
事業団」が提供する情報を転載しました。
――――――――――――――――――――――――――――
[退職金制度のコンサルティング] 中途採用が多い会社にピッタリする退職金制度の見直をお手伝いします。
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[見積] 30万円(税別) 33万円(税込)
[申込] https://nakagawa-consul.com/inquiry/index.html
または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
*************** 申込書*************************************
題 名 退職金制度のコンサルティング
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
************************************************************
――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――
今年は関東大震災が発生してから、丁度100年となる年です。
1923年9月1日11時58分、相模湾北西部を震源とする
推定マグニチュード7.9の地震が発生し、
東京、埼玉、千葉、神奈川、山梨で震度6を観測しました。
北海道道南や中国・四国地方でも揺れを感じるほどの
大地震だったようです。
地震発生時刻は昼食の時間と重なったことから、火災が多く
発生しました。さらに当日は日本海沿岸を台風が進んでおり
関東地方に強い風をもたらしたため、火は一気に燃え広がり、
東京・横浜は一面焼け野原となりました。
死者・行方不明者は約10万5000人にも及び、近年の大災害
(阪神・淡路大震災:約5,500人、東日本大震災:約1万8000人)
と比べても、その被害規模は極めて大きかったことが分かります。
関東大震災が発生した9月1日は「防災の日」と定められ、
日本における災害対策の出発点となりました。
100年後の私たちにもさまざまな教訓が受け継がれています。
――――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html