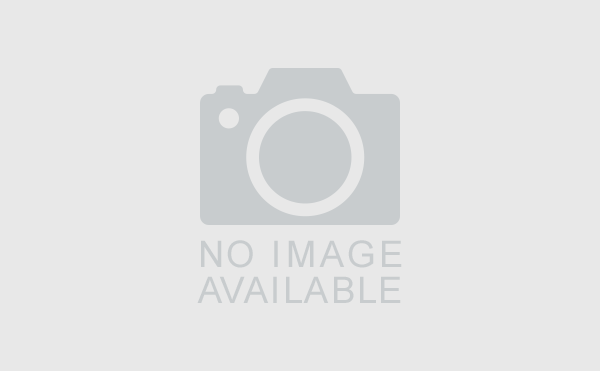上司のプライベートな質問、どこまで許される?
☆★☆―――――――――――――――――――――――――
「あの人はすごい!」と社長や上司が周囲から評価される
ピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業で20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場を駆け回った人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者:中川清徳 2025年2月3日 Vol.5859
――――――――――――――――――――――――――――
将棋盤の裏面の穴は何のためにあるのか?
(続きは編集後記で)
――――――――――――――――――――――――――――
[PR]
[オンラインWebセミナー]
[題名] オーナー経営者を守るための役員報酬・退職金の
見直し方セミナー
[対象] オーナー経営者、総務担当者
(プルデンシャル生命保険 多摩支社 ライフプランナー)
講師プロフィール
https://mylp.prudential.co.jp/lp/page/katsunori.hamada [価格] 20,000円 税別 (22,000円税込)人数不問
※メール顧問契約様は半額です。
https://nakagawa-consul.com/service/mail_adviser/ [日程] 2025年2月21日(金)10時00分~12時30分
[ 会場]オンラインWeb(双方向会議方式)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/078_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。 [オーナー経営者を守るための役員報酬・退職金の見直し方セミナー] 社 名
役職名
氏 名
参加数 人
(レジメは事前に郵送しますので必ずご記入ください)
電 話
郵便番号
所在地
ご希望日時
************************************************************
――――――――――――――――――――――――――――
上司のプライベートな質問、どこまで許される?
――――――――――――――――――――――――――――
皆さまの職場では、上司が部下のプライベートについて
過度に踏み込むことはありませんか?
「子供の学校の成績はどう?」
「奥さん(旦那さん)の年収は?」
「休日は何をしてるの?」
このように、仕事とは関係のない個人的なことを根掘り葉掘り
聞かれると、部下は精神的な負担を感じてしまいます。
中には「適当に流せばいい」と思う方もいるかもしれませんが、
行き過ぎた場合、パワーハラスメント(パワハラ)と
見なされるリスクもあります。
今回は、「上司と部下の適切な距離感」について考えて
みたいと思います。
1. 上司の質問が「ハラスメント」になるケース
職場において、ある程度の雑談や関係構築は必要ですが、
以下のようなケースではハラスメントに該当する可能性が
あります。
・業務に関係のないプライベートな話題を執拗に聞く
・答えたくないと示しているのに、何度も聞く
・職場の立場を利用してプレッシャーをかける
例えば、「共働きの配偶者の年収」などデリケートな話題を
しつこく聞かれると、部下は「なぜそんなことを知りたがる
のか?」と不安に感じます。家庭環境はデリケートな話題で
あり、人によっては触れられたくないものです。
2. 「親しさ」と「パワハラ」は紙一重
部下と良好な関係を築きたいという気持ちは理解できますが、
上司からのプライベートな質問が「業務命令のように感じる」
と、部下は断りにくくなります。
上司の立場としては、「親しみを込めて聞いているつもり」
でも、部下にとっては「避けにくい圧力」になっている場合が
あります。特に、答えなかったことで職場の人間関係に影響が
出ると感じた場合、それはハラスメントに該当する可能性が
あります。
3. 企業としてどのような対応が必要か?
では、このような状況を防ぐために、企業や労務担当者は
どのような対応をすればよいのでしょうか。
・就業規則やハラスメント防止規程に明記する
・「職務上必要のない個人的な質問を強要することは禁止」
といった文言を明記し、会社としての方針を明確にする
・管理職向けの研修を実施する
上司の意識を変えることが重要です。定期的なハラスメント
研修で、「どこまでが適切な質問なのか」「部下との距離感
をどう保つべきか」を学ぶ機会を設けましょう。
・相談窓口を設ける
部下が気軽に相談できる環境を整えることで、問題を早期に
発見・対応できます。社内に相談窓口を設置するほか、
外部のハラスメント相談機関を活用するのも有効です。
4. 上司として心がけるべき「適切な距離感」
上司が部下と良好な関係を築くために、プライベートな話題を
どのように扱うべきか、以下のポイントを意識するとよいで
しょう。
・仕事に関連する話題を中心にする
→「最近忙しいけど、仕事の進捗はどう?」など、業務の
話から自然に会話を始める。
・部下が話したい範囲にとどめる
→ 部下が自主的に話した話題を受け止めるにとどめ、
深く追及しない。
・部下の反応を見ながら会話を進める
→ 明らかに困った表情をしている場合は、すぐに話題を
変える。
非常に重要です。特に、業務に関係のないプライベートな
質問が、部下にとって心理的な負担となることを理解する
ことが求められます。
企業としては、ハラスメント対策を強化し、管理職向けの
研修、相談窓口の設置を進めることが、働きやすい職場
づくりの第一歩となります。
「親しさ」と「ハラスメント」の境界を意識し、互いに
尊重し合える職場環境を目指しましょう!
――[PR]――――――――――――――――――――――――
毎月無料!役立つ情報をお届け「ピカイチ情報通信」
――――――――――――――――――――――――――――
「ピカイチ情報通信」を毎月(休刊あり)メール送信に
より無料でお届けしています。
日刊メルマガとはひと味ちがった役立つ情報をお届けしています。
月刊「ピカイチ情報通信」をご希望の方は
下記より申し込んでください。
https://nakagawa-consul.com/nl/index.html
または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
*********** 月刊ピカイチ情報通信申込み**************
社 名
役職名
氏 名
郵便番号
所在地
電 話
******************************************************
――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――
将棋盤の裏面の穴は何のためにあるのか?
将棋盤は一見すると正方形に見えますが、実際には縦の方が
わずかに長く作られています。標準的な将棋盤のサイズは、
横が一尺一寸(約33センチメートル)、縦が一尺二寸(約36
センチメートル)であり、俗に「尺一尺二」と呼ばれています。
この正式な将棋盤を裏返すと、中央に四角いくぼみ(穴、彫り
込み)があることに気づきます。このくぼみは俗に「血溜り」
と呼ばれています。その由来として、昔、将棋を観戦して
いた者が対局者に助言をした場合、その首をはねてこの
くぼみに据えたとされ、血がそこに溜まったことから
「血溜り」と呼ばれるようになったという説があります。
しかし、これはあくまで俗説であり、実際には信憑性に
欠けるものです。
では、このくぼみは何のためにあるのでしょうか。
一般的には、以下のような説が挙げられています。
1. 駒を打ち下ろしたときの音をよくするため
2. 盤のゆがみや割れを防ぐため
特に、木製の将棋盤は乾燥や湿気の影響を受けやすく、
適切に反りやひび割れを防ぐ構造が求められます。そのため、
裏面にくぼみを設けることで、木材の伸縮を調整し、盤の
耐久性を高める役割を果たしていると考えられます。
このように、「血溜り」の由来にはさまざまな説があります
が、実際には将棋盤の機能を向上させるための工夫の一つ
であると考えるのが妥当でしょう。
(知って得しない話。 北嶋廣敏著 グラフ刊より)
https://amzn.to/36d1AGR
――――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
難解な法律条文や判例をわかりやすくするために、
簡略化した説明を行うことがあります。
簡潔な説明を重視しているため、詳細は専門家へご相談
いただくことをお勧めします。
このメルマガ記事に基づく損害やトラブルについて、一切の
責任を負いかねます。
――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト
☆問い合わせ
info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー
☆登録・解除
社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 - メルマガ
大企業20年、中小企業13年、人事労務担当一筋で現場をはいずりまわった経験を活かし、中小企業の経営者、管理者のための人事労務管理について、すぐに役立つピカイチ…